子育てをしていると、よく聞くのが「イヤイヤ期」という言葉。
なにを言っても「イヤ!」と返されたり、泣いたり、怒ったり…頭を抱える保護者さまも多いでしょう。
しかし、このイヤイヤ期は子どもにとっても成長の大切なステップなんです。
今回はイヤイヤ期になる時期やその原因、子どもがイヤイヤ期になったときの乗り越えるコツなどをご紹介します。
前回の記事はこちらから!
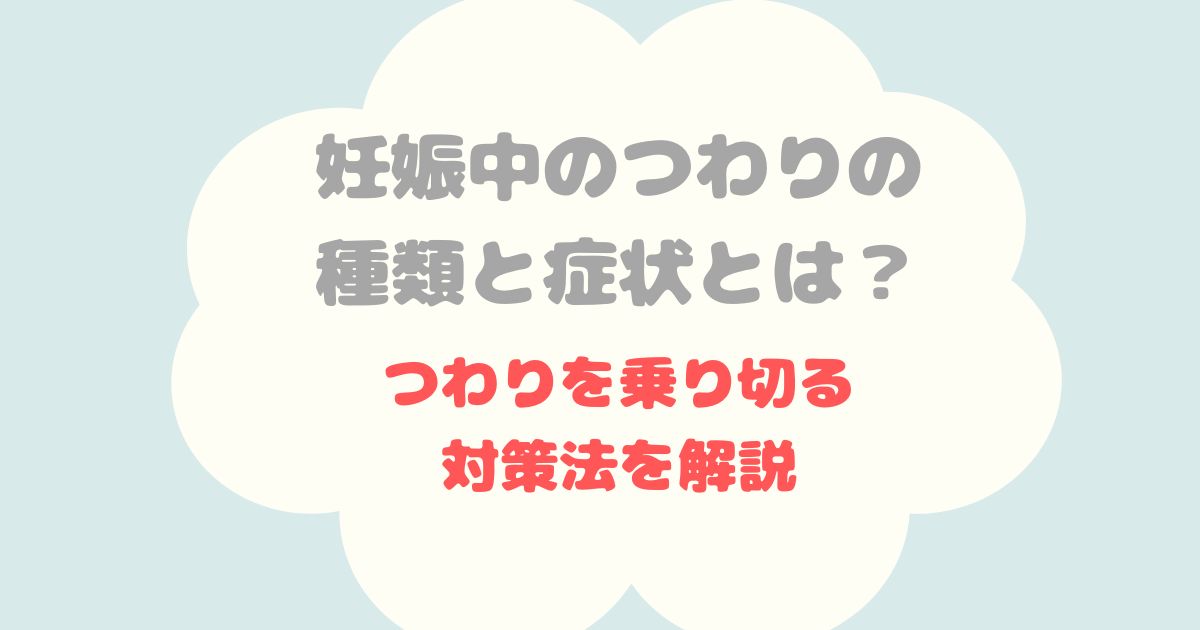
イヤイヤ期はいつから始まっていつ終わる?

「イヤイヤ期」は、だいたい1歳半ごろから3歳前後に始まります。個人差はありますが、多くの子どもが2歳になる頃にははっきりとしたイヤイヤ期が始まると言われています。
だからよく「魔の2歳児」なんて言われることもあるんだとか。
そして、気になるのが「イヤイヤ期はいつまで続くの?」ということ。目安としては、3歳~4歳ごろまでには落ち着くことが多いです。
しかし、子どもの性格や環境によって5歳ごろまで続く子もいます。
実は「イヤイヤ期っていつまで続くの?」と感じるのは親も子も成長している証。終わりの見えないトンネルに思えるかもしませんが、必ず終わりはくるので安心してください。
イヤイヤ期の原因

子どものイヤイヤ期は、ただワガママを言っているわけではありません。
このイヤイヤ期の大きな原因は『自我の芽生え』です。
子どもはこの時期に、自分の考えや気持ちを持ち始めます。でも、まだ言葉でうまく伝えることができないため「イヤ!」というシンプルな言葉で、自分の気持ちを主張しているんです。
たとえば、「自分でやりたいのにうまくできない」「やりたくないのにやらなくちゃいけない」などの気持ちが隠れているのかもしれません。
つまり、イヤイヤ期は成長の証なんです。
イヤイヤ期を乗り越えるコツ5選

「イヤイヤ期は子どもの成長だと理解しているけど、どうすればいいか分からない」という保護者さまもいるでしょう。そこでここでは、イヤイヤ期を乗り越えるためのコツを5つ紹介します。
共感してあげる
子どもが「イヤ」と言うのには必ず理由があります。まずは、子どもの気持ちに共感してあげることが大切です。
ポイントは、「もっと遊びたかったんだね」「悔しかったよね」と子どもの気持ちを言葉にしてあげることです。そうすることで、子どもは「分かってもらえた」という安心し、また次に同じ感情になったときに言葉で伝えられるようになります。
自分で選ばせてあげる
「服をきて!」と言われると「イヤ」となってしまうのがイヤイヤ期の特徴。これが世のお母さんを悩ませる大きな原因といっても過言ではないでしょう。
そんなときは「赤の服と青の服だったらどっちがいい?」と2択の選択肢を与えましょう。2択にすることで混乱も減り、自分で選ぶ力も育むことができます。
事前に報告する
子どもは今していることを急に止めるのが苦手です。たとえば遊んでいるときに「おでかけしよう」と言っても「まだ遊んでいたいのに!」となってしまいます。ですが、次に何が起きるかを伝えるだけで、ぐっと落ち着くことがあります。
たとえば、「あと5分したらお風呂に入ろうね」「この音楽が終わったらご飯にしよう」など事前に報告しておくことで子どもの「イヤ」が減ることがあります。
まだ時計が分からない子は砂時計やタイマーなどを使うと効果的です。
できるだけ自分でやらせてあげる
イヤイヤ期の子どもは「自分でやりたい」という気持ちがとても強いです。たとえ失敗しても、やらせてみることが大切です。
とは言っても時間がないときはゆっくり見守ることも難しいでしょう。その場合は「保育園から帰ってきてお買い物に行くときに、自分でくつを履いてみよう」と約束をしてあげましょう。手が出したくなる場合でも「自分でやった」経験が自信につながるので優しく見守ってあげましょう。
気分転換のチャンスをつくる
子どものイヤイヤが止まらないときは、気分を切り替えることも効果的です。場所・遊び・話題を変えるだけで空気が一気に変わることがあります。
たとえば、一回外に出て風を感じたり音楽をかけて一緒に歌ったりすると、子供も親もリフレッシュすることができるのでおすすめです。
まとめ

- イヤイヤ期が始まるのは1歳半ごろ、ピークは2歳前後
- イヤイヤ期は一般的に3歳~4歳で落ち着く
- 原因は「自我の芽生え」で成長している証
- 無理に抑えず、気持ちを受け止めてあげることが一番の対処法
「イヤイヤ期」は、子どもが心の中で「自分」を育てている証拠です。
「イヤ」という言葉の奥にある気持ちを理解して、うまく向き合えば、親子の関係もぐっと深まるでしょう。
イヤイヤ期は大変で保護者さまは心身ともに辛くなる時期でもあります。しかし「今しか見れない姿かもしれない」と前向きに捉え、乗り越えていきましょう。
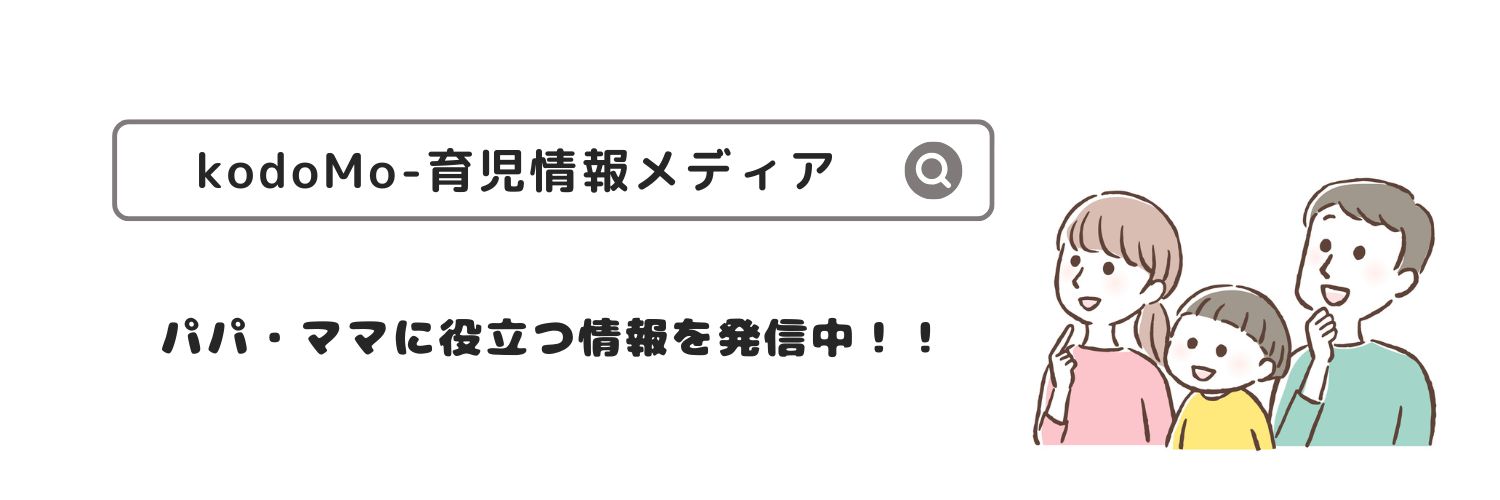
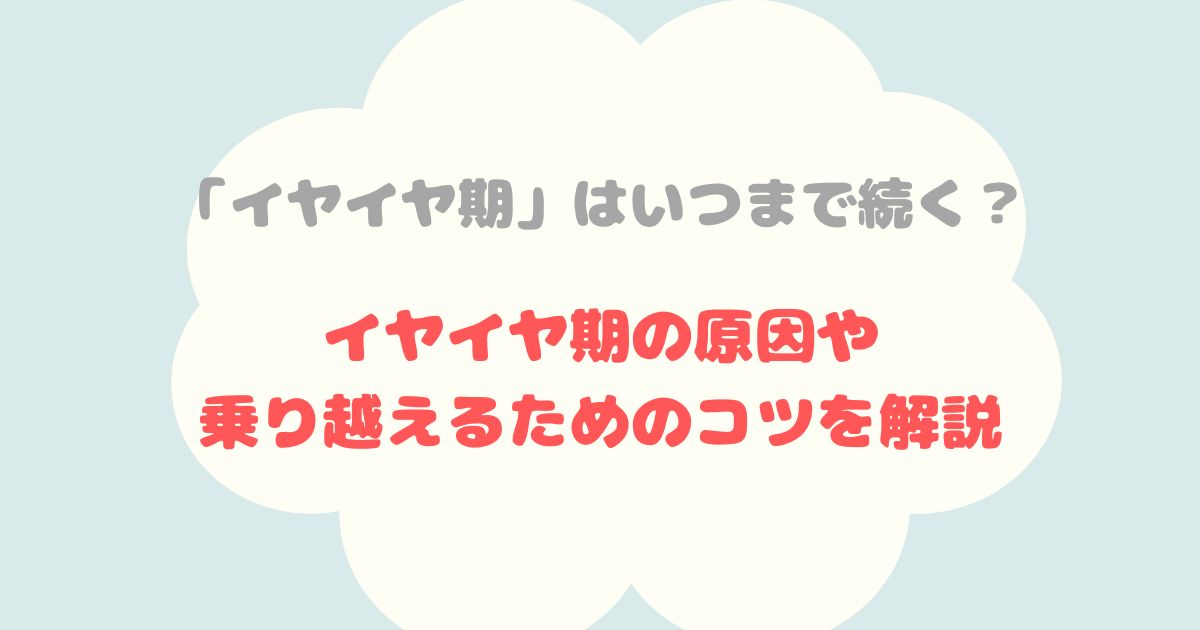
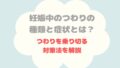
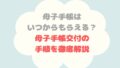
コメント